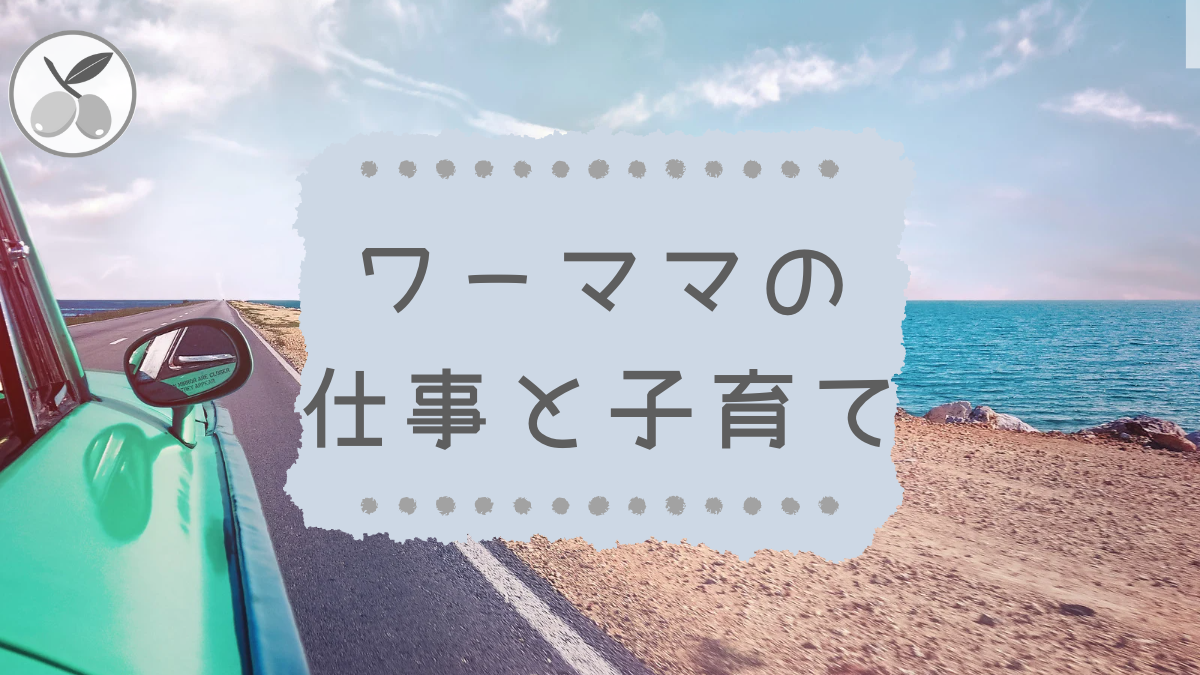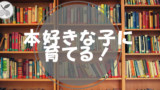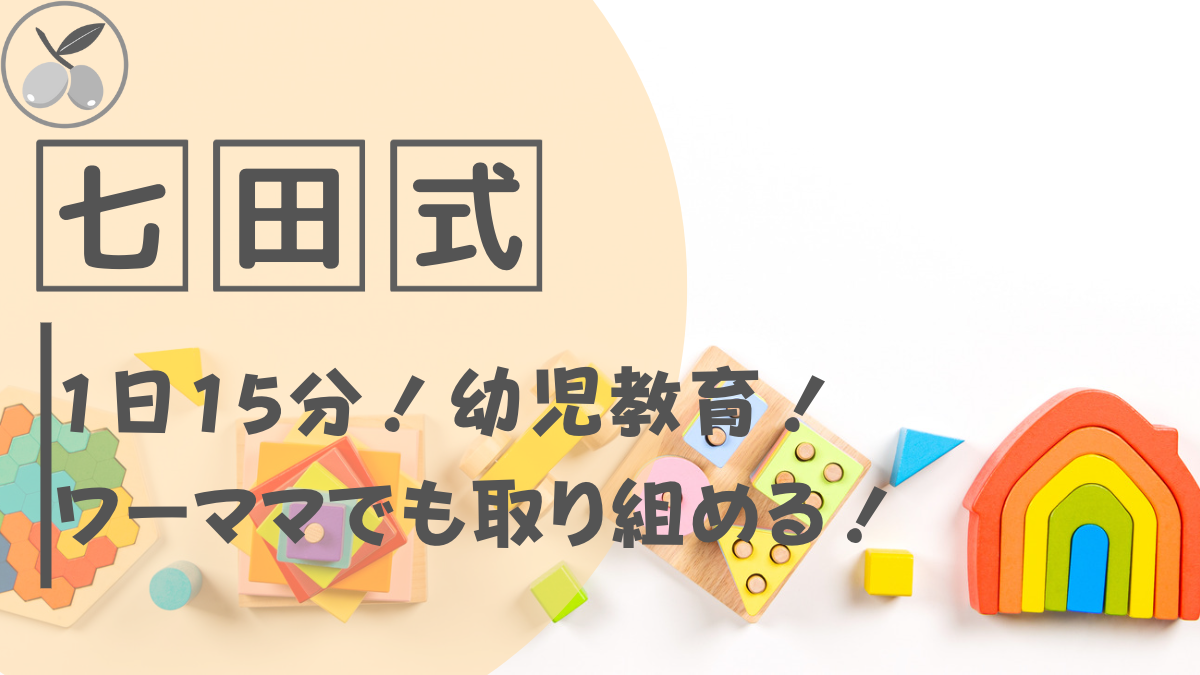広告代理店勤務のフルタイムワーママです。育休復帰後は、多少の子持ち配慮があるものも業務内容は独身時代と変わらず、属に言うサラリーマンの男性と同じように働いていました。
夫にお迎えをお願いできる時以外は定時で帰りますが、社用スマホも定時で終了という訳にはいかず、場合によっては帰宅後も電話応対やメールのやりとりがあります。
割と過酷な部類の労働をしているワーママですが、幼児教育をする教育ママでもあります。趣味は子供の習い事。0歳から公文式、3歳からピアノ・バレエ・スイミングを行っています。
長女は1歳〜3歳まで小規模保育園、年少々からモンテッソーリ幼稚園へ転園。年中でお受験国立幼稚園へ転園しました。
こんな私が考える、ワーママ×子育ては時間捻出がカギ。
当たり前のことですが、専業主婦と違い子育てに携わる時間が圧倒的に少ない中で、帰宅してからの残された時間、何を優先にするべきか、試行錯誤しながらやってみました。
①20時半〜21時に就寝を目標にする(10時間以上の睡眠確保)
3歳〜6歳では個人差はあれど11〜13時間の睡眠が必要と言われています。睡眠不足は成長への悪影響、集中力や記憶力の低下などデメリットだらけ。
現状、その子にとって適した睡眠時間を十分に取れているか確認し、必要な睡眠時間をしっかりと確保しましょう。そして、寝る時間と起きる時間をちゃんと決めましょう。
保育園で2時間ほどお昼寝をしていることを考慮し、家では10時間以上睡眠を取れるようスケジュールを組みましたが、とても大変で上手くいかないこともありました。
私は「昨日は何時間寝たかな?」と計算するほど睡眠時間に凝っていました。が、あまりにも凝りすぎてしまうと、「早く!早く!」と急がせるママになってしまい、子供にとってお家時間が楽しくないものになってしまいます。
「○時間寝かせよう」と目標は決めるもののあまり囚われすぎず、子供と楽しく過ごすこと、一日の疲れを癒やし明日に向けて前向きな気持ちでいられることを意識しましょう。
読み聞かせが止まらず、結局21時半に寝ることも多々ありました。
そしてもし、今すでに寝不足であるなどトラブルがある場合は、生活スタイルの改善や時短勤務などを行い改善させましょう。
②絵本の読み聞かせ時間を確保
「保育園に通わせたことを不憫に思いたくない」思いからどうすれば、離れている時間の穴埋めができるかと真剣に悩み、調べたどり着いたのが読み聞かせでした。
読み聞かせのメリット
・語彙力が増える
・集中力がつく
・想像力を育む
・感情が豊かになる
・自己肯定感が高まる
・コミュニケーションがとれる
などありますが加えて、読み聞かせによって母親の愛情を感じ安心できる、親子のスキンシップがとれるため共働き世帯にはぜひやってほしいです。
ベビー公文よりワーママの挑戦!「うた200 読み聞かせ1万 賢い子」を目標にしてきたため、5冊以上の読み聞かせをしてきました。
睡魔との戦いで、途中で値落ちしてしまい長女に起こされたり、間違った文章を読み「違うよ!〇〇でしょ」と指摘されることも多々ありました。
この読み聞かせによりスキンシップをとれたことで、あれだけ私が男性並に働いたにも関わらず天真爛漫な良い意味で気の強い子に育ってくれたと思います。
あの頃、安心感や情緒の安定を支えてくれたのはまさに読み聞かせです。
年中5歳では、公文の先生に「かなり語彙力があり、難しい文章もスラスラ読めます」と褒められるほどに。
③お勉強の時間を確保
必ず確保したいお勉強の時間ですが、色々試した結果うまくいかなかったため、帰宅後は絵本の読み聞かせに集中し、お勉強は朝にしました。
朝のお勉強は、七田式プリントです。七田式プリントも幼児教育の一貫ではありますが親子で取り組むため楽しくおこなうことができます。
長女にとっては「ママと遊んでいる」感覚だったようです。
長女は6時半に起床し、私と一緒に七田式プリントに取り組むのを日課にしました。
「朝起きてすぐ!?」と驚かれる方もいるかと思いますが、朝起きてからの3時間が脳にとってゴールデンタイムと呼ばれ最も効率よく情報が吸収できる時間帯です。
また、思考の回転が早くドーパミン・アドレナリンといった神経伝達物質が分泌されていると言われています。
なにより、体力・気力共に一番充実しており、脳が1番リフレッシュした状態であるため、時間がないワーママが幼児教育に取り組むなら朝が一番オススメです。
ママにとっても、朝は来客・電話・ラインなど人に邪魔されることがないため、子供との時間に集中できます。
④親子のスキンシップを欠かさない
帰宅後は詰め込みすぎないこと!
1日の疲れを癒やし、ご飯とお風呂、一緒に遊ぶなどゆっくり過ごします。
仕事の延長で、帰宅後も家事をフルパワーで行いがちですが、ご飯を食べながらの会話や、お風呂で一緒に遊ぶなど、楽しむ気持ちを忘れないようにしましょう。
そして、子供の出すサインを見逃さないようにします。
「保育園で楽しく過ごせているか。」「何か困っていることはないか。」「言いたいけど言えないで我慢していることはないのか。」
1日の大半を過ごす保育園では楽しいことだけではなく、我慢することも納得できないことも経験しながら集団の中で頑張って過ごしています。
ママが時間に追われ忙しくしていると、子供は言い出せないこともあります。
外で頑張っている分、家ではワガママに甘えれる、落ちつく場所を作ってあげましょう。
「明日も楽しい事がある!」と思って就寝できるのが理想なので、あまり予定を詰め込ませないようにしています。
「あ〜。今日も1日疲れたね〜。」と子供と一緒にゴロゴロするのも時に大事です。
休む方法や休み方を知ることができます。
洗い物や部屋の片付けができていなくてもOK。心の健康が何より大事!上手くサボりながら、親子のスキンシップを深めましょう。
①自分の時間確保
意識しないと自分の時間なんて全く取れません。
私は朝活をすることで自分時間を確保しています。(2歳の時はわたしが布団から出ると察して起きるためなかなか難しかったですが…。)
朝起きて一番最初にやることは、自分の好きなこと。自分の好きなことが出来ると、それだけでリフレッシュになりますし、気持ちに余裕ができます。
子供にとって一番良い環境とは「母親が笑顔で明るく楽しく暮らしていること」
母親がいつもピリピリして疲れ切っている状態では、子供は伸び伸びと自己表現をすることはできません。そのような環境では幼児教育も子供にとって逆効果になってしまうことも。
子供のために、自分を犠牲にして辛い思いを続けるのも危険です。
母親が機嫌が良いのが子供にとって一番の教育
趣味やリフレッシュなど自分時間を確保して笑顔でいれるよう心がけましょう。
②掃除・洗濯・洗い物に妥協する
私は、仕事をしながら幼児教育をすると決めたため、家事は妥協することにしました。
洗濯物は基本干しません。
どうしても乾燥かけたくない服は干しますが、平日仕事でそのような服は着ません。
子供服も幼稚園に着ていくものはユニクロやプチプラなど、乾燥して縮んでも気にならない服にしています。
料理をする余裕がない時はしません。洗い物をする気力がない時はしません。
元々、私より夫の方が料理も得意なため、お任せするようにしています。
家事を完璧にやらなければいけない脅迫概念のようなものに囚われると、夫婦間でも相手の粗探しが増え家庭内も不平や不満ばかりになります。
優先順位の共有も必要です。
1位 こども・幼児教育 2位 家族 3位 仕事
などのように、夫婦で同じ優先順位を持つようにしましょう。
家族のための家事が、家族を苦しめる家事にならないように。
最後に…
ワーママは、時間捻出に効率化にルーティン化…etc 本当に大変!!!!!
大変ですが、やりがいと達成感も沢山!!!!!
社会で生き抜くための知恵と大事なことを子供に教えることもできます。
母親が生き生きと仕事をし、家族との時間を楽しみ、愛情と笑顔が溢れる家庭であることがなにより大事です。
今日も楽しみながらがんばります。