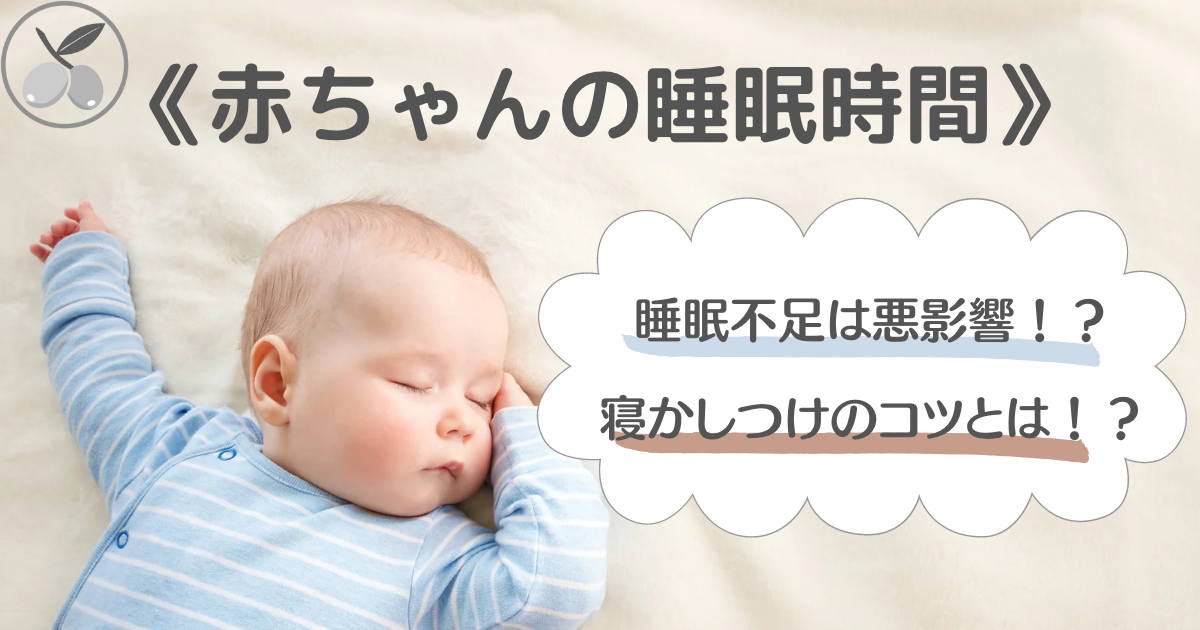新生児期には1日の大半を寝て過ごす赤ちゃんも成長と共に起きている時間が増えてきます。
起きている間に色んな物を見て、触って、刺激を受けますが、その経験は眠ることによって記憶に残り定着します。
赤ちゃんの睡眠時間 が大事な理由とは
睡眠には、レム睡眠とノンレム睡眠の2種類があります。レム睡眠は脳が活動している浅い眠り、ノンレム睡眠は脳が休息している深い眠りです。
子どもは大人よりもレム睡眠の割合が多く、レム睡眠中に脳の神経回路が生成されます。
そしてノンレム睡眠中に成長ホルモンが分泌され体と脳の成長を促しています。赤ちゃんはレム睡眠の間に脳を創り、記憶や認知などの機能を進化させています。
〚主な睡眠の役割〛
①脳幹を活発にさせる役割…頭の中の神経回路を広く繋げ、脳を育てる。
②情報を仕分ける役割…起きている間の経験を記憶させ、知識化する。
良い睡眠を取ることにより、認知力は向上し感受性も育ちますが、十分な睡眠がとれない赤ちゃんはイライラしたり神経質になってしまいます。
また、生後4ヶ月くらいからは成長ホルモンが分泌されます。成長ホルモンは睡眠の他で補うことができず、この成長ホルモンによって筋肉や骨を育て、細胞を修復させ赤ちゃんの成長を手助けします。
丈夫な体を育てるため、賢い頭を創るために睡眠はとても大事です。
生後1年の脳の発達は目覚ましく、また3才までに約8割が出来上がってしまうと言われています。赤ちゃんはもちろんですが、幼児期には十分な睡眠をとることが重要です。
睡眠確保のためにすべきこと
1,スキンシップで愛情形成
スキンシップとは和製英語で、皮膚と皮膚が触れることで快感を得ることを脳科学用語では「C線維カレス系」(システム)とい呼ぶそうです。(「赤ちゃん教育」の久保田カヨ子さんの著書で知りました。)カレスとは英語で慈愛の情を起こす行為を指し、キスや抱擁、なでることを指します。
皮膚がふれるように抱き合うと双方のC線維カレス系(システム)が働き、お母さんも赤ちゃんも気持良くなります。
泣いている時に抱くことも不安が解消され、安心感につながります。
肌と肌のふれあいを大事にし、ベビーマッサージなども取り入れ、日頃から安心感を与えてあげるようにします。
2,十分な食事と運動
泣きながら寝る、ぐずって寝るよりも段々といつの間にか寝るほうが情緒の面からも良いと言われています。
離乳食やミルクの量は適切か、お腹が空いた状態ではないか確認をしましょう。
満腹、おむつもキレイな状態で機嫌が良いのが理想です。
そして、よく眠るためには運動も必要です。ボールを転がしてハイハイをさせたり、ボールをキャッチさせる、顔だけでなく体を使っていないないばぁをする、歌に合わせてリトミック、お散歩など。
刺激を与える遊びがちょうどいい運動になります。
沢山の刺激を受けたあとは、脳も疲れて「すーー。」っといつの間にか寝てくれます。
これがまさに、起きている間の刺激を睡眠中に記憶し知識化することになります。
3,睡眠環境を整える
寝心地が悪くて途中で目覚めてしまう、睡眠を妨害されることがないよう睡眠環境を整えます。
温度・湿度は適切か温度計を設置して確認しましょう。
冬場の乾燥は風邪にもつながるので、加湿器を使うことをおすすめします。
また、クーラーが直接当たらない場所にベビーベッドを設置します。サーキュレーターを使うと空気を均一に循環させてくれて、クーラーの効果も高まり節電にも繋がります。
また、寝具も確認しましょう。
乳児の添い寝は危険を伴うためベビーベッドをおすすめします。
長女の時はリビングに布団を敷いて寝かせていましたが、次女の時は5才になった長女が走り回り、足音もうるさいため簡易用ベビーベッドを購入し、日中リビングでの昼寝用、寝室用、とわけました。
日中のベビーベッドは折りたたみができ持ち運びもできるタイプです。
こちらで紹介→《2人目出産》新たに買い揃えたもの&よく使ったものを紹介
移動もでき、ゆりかご機能もついているため、大活躍。
新生児は特に1日の大半を寝て過ごすことになるので、寝心地の良さが大事です。日中の睡眠妨害にならないよう、快適な寝具を用意しましょう。
寝かしつけのコツとは!?
初めての育児で一番大変だったのは寝かしつけでした。長女の時はかなり苦戦しました。
誰だって眠くない時に寝るのは無理。
まずは赤ちゃんの睡眠サイクルを把握し、こちらが合わせることでストレスはぐっと減ります。
いつもなら寝ている時間に外出しお昼寝が出来ない、途中で起こされてしまった、などサイクルが崩れると機嫌も悪くなりその後の寝かしつけも大変になります。
新生児は授乳・オムツ交換→睡眠の繰り返しですが、4ヶ月を過ぎるころからは段々と睡眠サイクルに変化が現れるのでその子の睡眠量を把握してあげましょう。
午前中に◯時間の昼寝、午後に◯時間の昼寝を◯回など把握することにより「そろそろ寝る頃だな。」とサインがわかります。
《理想の寝かしつけスタイル》
①体と頭を使った遊びをする
ベビー体操・ハイハイ・リトミック・歌など体を使い脳へ刺激を与える遊びをする。
②ご飯またはミルクや授乳
頭と体を十分に使ったあとにお腹を満たします。
③そのまま入眠
授乳中に寝るパターンが8割。トントン寝、ドライブで昼寝など方法は色々ありますが、十分に遊んで腹ごしらえをした後は寝かしつけが楽ちん。
逆になかなか寝てくれない時は、「遊び足りなくて疲れていない」「お腹が空いている」のどちらかのパターンが多くありました。
夜の寝かしつけがうまくいかない時も一度諦めて、10分でもいいのでちょっと一緒に遊ぶ。そしてからミルクを飲ませ寝かしつけするとすーっと寝てくれました。
長女の時の私は、寝る気のない長女を相手に「なんで寝てくれないの〜。」と思いながら寝かしつけを続けていました。
赤ちゃんは母親の気分を察するようです。お母さんがオドオドしたり、イライラすると寝かしつけはスムーズにいかないため、心に余裕を持つことが大事です。
「赤ちゃん教育」著者の久保田カヨ子さんは「よく寝る子は育つ」ではなく「いつの間にか寝る子は育つ」と言葉を残されています。
泣きながら寝る、グズって寝るのはあまり良い例とは言えず、機嫌が良い状態でいつの間にか寝るのを理想とされています。
因みに…わが家は姉妹ともおしゃぶりNGな子だったため入眠おしゃぶりなどは上手くいきませんでした。
最後に・・・
やっとのことで産まれてきてくれたかわいいわが子。
将来はこんな子になってほしい。こんなことを一緒にしたい。賢い子になってほしい。など色々な思いがあると思います。
何をするにも、大事なのは丈夫な体と賢い脳だと思います。
丈夫な体と賢い脳を創るのは有名な塾に通わせる事や習い事で英才教育することではなく、適切な時期の適切な睡眠です。
人生で一度きりのゴールデンタイムを逃すことがないよう睡眠を意識しましょう。