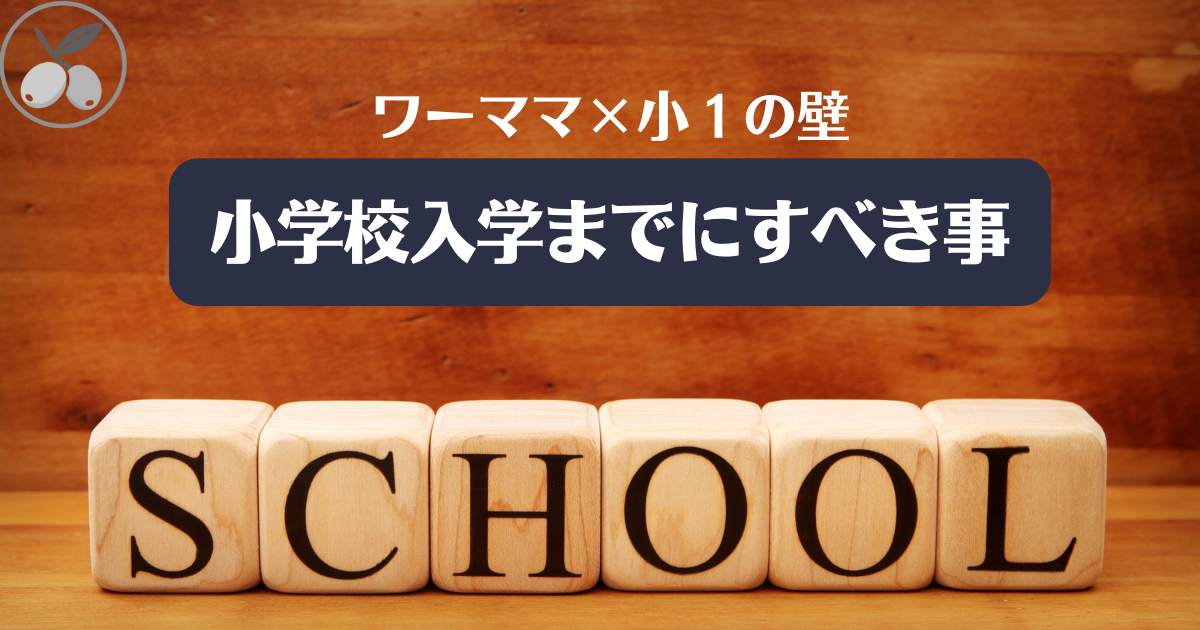小1の壁 とは!?
小1の壁 というフレーズをよく聞きます。
小学校に入ってからの預け先・学童問題、宿題への対応、長期休みをどうするかなど、親の出番が多く、フルタイムを断念するタイミングでもあるためこのように呼ばれていますが、本当に壁を感じているのは実は子ども自身。
これまでの流れで小学校に臨んでしまうと、子どもは大きな変化に戸惑ってしまい、学校生活を楽しく送れなくなってしまう恐れがあります。
トラウマなど抱えないためにも、年長時期から小学校への準備を親子で進めていきましょう。
小学校の役割とは!?これまでと何が違う?
小学校への入学は親子共々大きなステップとなりますが、一番大きな違いは評価を受ける点だと考えます。
幼稚園・保育園では、心と体の発達を促す遊びがメインで、個々の成長に先生方が寄り添ってくれる体制であったのに対し、小学校は勉強や運動を通じ競争する場面が多くあります。また、型にはめる教育であるため集団の中での自分の在り方を知ることとなります。
勉強と生活態度の両面より先生が評価をつけ、集団の中でどの位置にいるのか、何が優れていて何が劣っているのかを知らされることになります。
面談でも良いことも悪いことも言われるため、親にとっても身が引き締まる思いです。
保育園の役割…日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること
幼稚園の役割…幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長すること
小学校の役割…各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自律的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うこと。
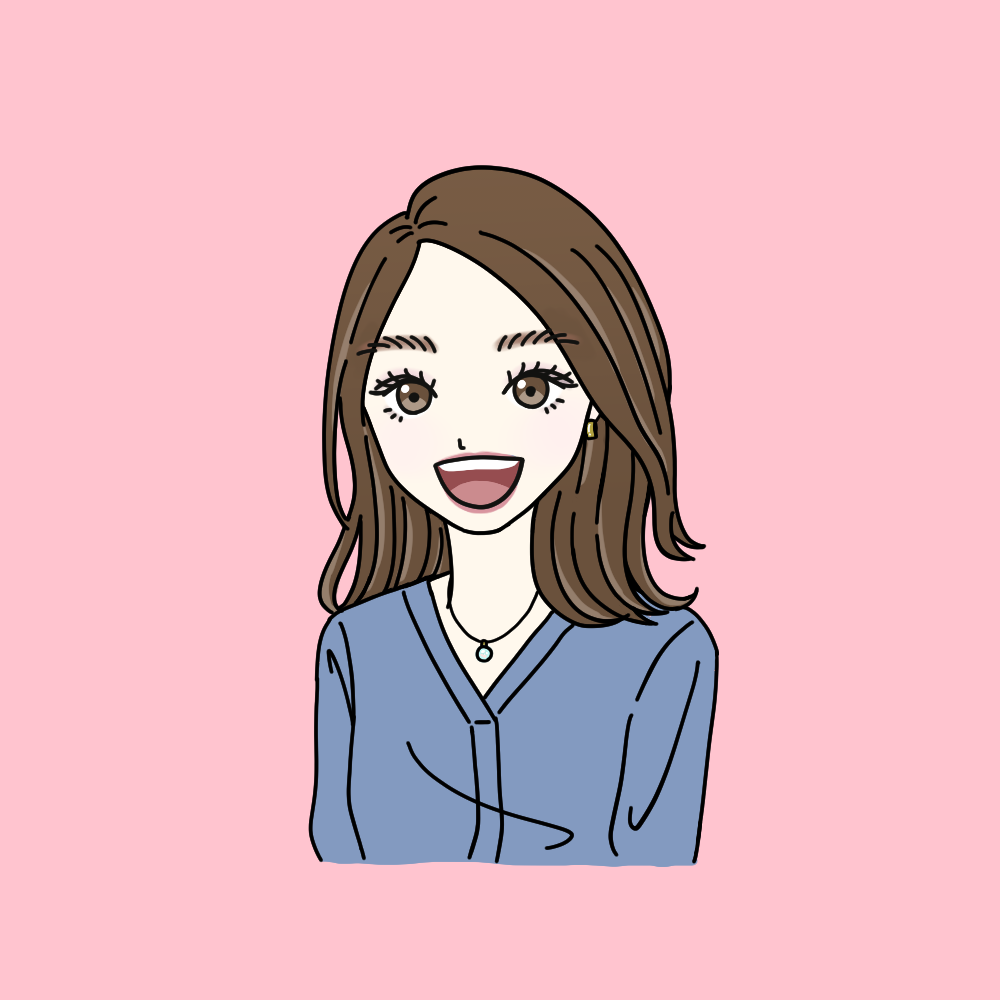
「型にはめる教育」って今の時代どうなの?と思う部分がありますが、教育機関の改革はなかなか進まないため、「型にはめる教育」の犠牲にならないよう家庭でのサポートが大事!
保育園ではみなぎる体力の限り走り回り、先生の話を聞くことを知らず、自分の遊びに没頭してしまうタイプの子は、ただ「体力のある元気いっぱいの子」でしたが小学校では「〇〇君、話を聞いてください。」と注意を受けることになります。
好き嫌いが多い、食が細く、ゆっくり給食を食べていた子は、小学校に入ると給食に苦戦します。午後はお腹を空かせ授業が頭に入らなくなってしまったり、給食が原因で学校が嫌いになってしまう可能性もあります。
最初は肝心で「ちょっとした出来ない」が自信喪失につながり学校が嫌いになる、集団の中に溶け込めず浮いてしまうことでからかいの対象になってしまう。
特にこどもは素直な故に時に残酷な発言をすることが多々あります。何事も始めが肝心ですので、良いスタートを切れるよう準備をしましょう。
小学校入学までに何をすればいいの!?
具体的にどんな準備をすればいいのか。基本的には保育園・幼稚園の延長であり身の回りの事ができ自己管理ができれば問題ないと思います。
過度な先取り学習である必要は全くないですし、軍隊のように規則正しく行動を叩き込む必要もありません。
慣れ親しんだ保育園・幼稚園を離れ、新しい環境で新しい友だちとの生活がスタートするので子ども達の心は少なからずストレスを感じています。
環境が変わることで、不安から、いつも出来ることが出来なくなってしまう恐れがあります。
「小学校では〇〇をするんだよ。」「一人で〇〇してみようね。」と事前に知らせ予行練習をすることでこどもも心の準備ができ不安を取り除くことができます。
事前に予行練習をすることで、学校で先生から「やってみてください。」と言われた時にすぐ反応できるため自信につながります。「学校って楽しい。」と思うきっかけや自信にもつながります。
具体的に小学校入学で困らないためにどのような事をすれば項目にわけてまとめてみました。
身の回りのことについて
・早寝早起きができる
・一人で着替えができる
・脱いだ服をたためる
・ご飯を時間通りに食べれる
・身支度を自分でできる
・朝トイレに行く習慣をつける
ほとんどが朝の準備に関係する内容となっています。
体育の授業では休み時間内に着替えを終わらせないといけなくなるので、着替えに時間がかかっている子は日頃から練習が必要です。
わが家では、着替えの最中に他のことに意識が飛びなかなか進まないためタイマーをセットし「2分以内に着替えようね。よーいドン!」とし、時間内に着替えをする癖付けをしました。
学校生活について
・自分の持ち物の管理ができる
・はさみやのりなど必要な道具を使う
・傘やカッパをたためる
・ひもを結ぶ、リボン結びができる
・ご飯をよそうこと、配膳ができる
・雑巾を絞って使うことができる
・ほうきやちりとりを使うことができる
・和式トイレを使える
・文字を読み必要な情報を得ることができる
・数の概念を持ち、数を数えることができる
出来ない時は親や先生が手助けしてくれていたのが、なんでも自分でやらなくてはいけなくなります。物の管理、物の正しい使い方をマスターするようにしましょう。
また、靴のタイプに限らずリボン結びはできるようにしておきましょう。学校によってはプリントの綴じ紐、行事に使う衣装など思わぬ場面で使う機会があります。
和式トイレも同様。最近の小学校はほとんどが洋式トイレになっていますが、遠足先で和式トイレに遭遇する場面もあるため、どちらでも対応できるようにしておきましょう。(和式トイレは数も少ないため、見つけたら使うようにするといいと思います。)
文字から情報を得る、数の概念についても、日頃からこども自身にさせることをおすすめします。「なんて書いているの?」と聞かれて答えてあげるのではなく、一緒に読んでみて「どういうことかな?」と理解度をチェックしてみましょう。
人間関係・コミュニケーションについて
・挨拶、返事ができる
・やりたいこと、困っていることを人に伝えることができる
・人の話を聞くことができる
・話の内容を理解し行動に移すことができる
大きな声で挨拶をするだけで意欲的、返事をするだけで理解していると捉えられる節があります。
もちろんこれが全てを物語っている訳ではありませんが、悲しくもそのまま評価につながってしまうこともあります。
そして、先生1人に対し30人前後のこども達がいるの中で「わかりました!」「理解しました!」とアピールするためには一番手っ取り早い方法であります。
一番大事なのは、インプットとアウトプット力。学校でその日あったことをすべて親が把握するのは不可能です。
話をよく正しく聞き、相違のない行動をとることは低学年にとって難しいものです。これは日頃から自立しているか否かが試されます。
「自分がやならなくてはいけない」という当事者意識をもつことが大事です。あまり手をかけすぎず、自ら実行する習慣をつけていきましょう。
勉強・運動について
・姿勢良く椅子に座ることができる
・正しい鉛筆の持ち方ができる
・自分の名前を読むこと、書くことができる
・大体のひらがな、カタカナの読み書きができる
・走る、跳ぶ、投げる、蹴る、縄跳び、ケンケンパ、でんぐり返しの動作ができる
・顔に水がつくことを嫌がらないでできる
まず大事なのは授業時間中に座っていられることです。
これは集中力の問題よりも、筋力・体力の問題のほうが大きいです。日頃からソファーでくつろぐことが多いと、座るために使う筋力が発達していないこともあります。
机と椅子を用意し、座るくせ、座って作業をするくせづけをしましょう。
名前の読み書き、ひらがな、カタカナについても、小学校で学ぶ内容ではありますが幼児期のうちにマスターしている子は多くいます。
最初が肝心で、スタートダッシュで「自分は出来ない」と思ってしまうと「勉強は苦手・嫌い」という意識を植え付けかねません。
家庭でのサポートをおすすめします。
ひらがなは読めるけど書くのがまだというお子さんには七田式プリントBがおすすめ。
七田式プリントについてはコチラ→【七田式プリント】1日15分!ワーママでも取り組める幼児教育
交通・安全面
・自宅から学校までの道順がわかる
・交通ルールを守れる
・何が危ないかを予測し回避できる
・交番の場所、困った時に駆け込む場所がわかる
・必要な時には自分の住所や電話番号を伝えることができる
・見知らぬ人にはついていかない、誘惑されても断ることができる
親の1番の心配である交通・安全面。スマホやアップルウォッチを持たせたいところではありますが、なかなか許可をしてくれない現状があります。
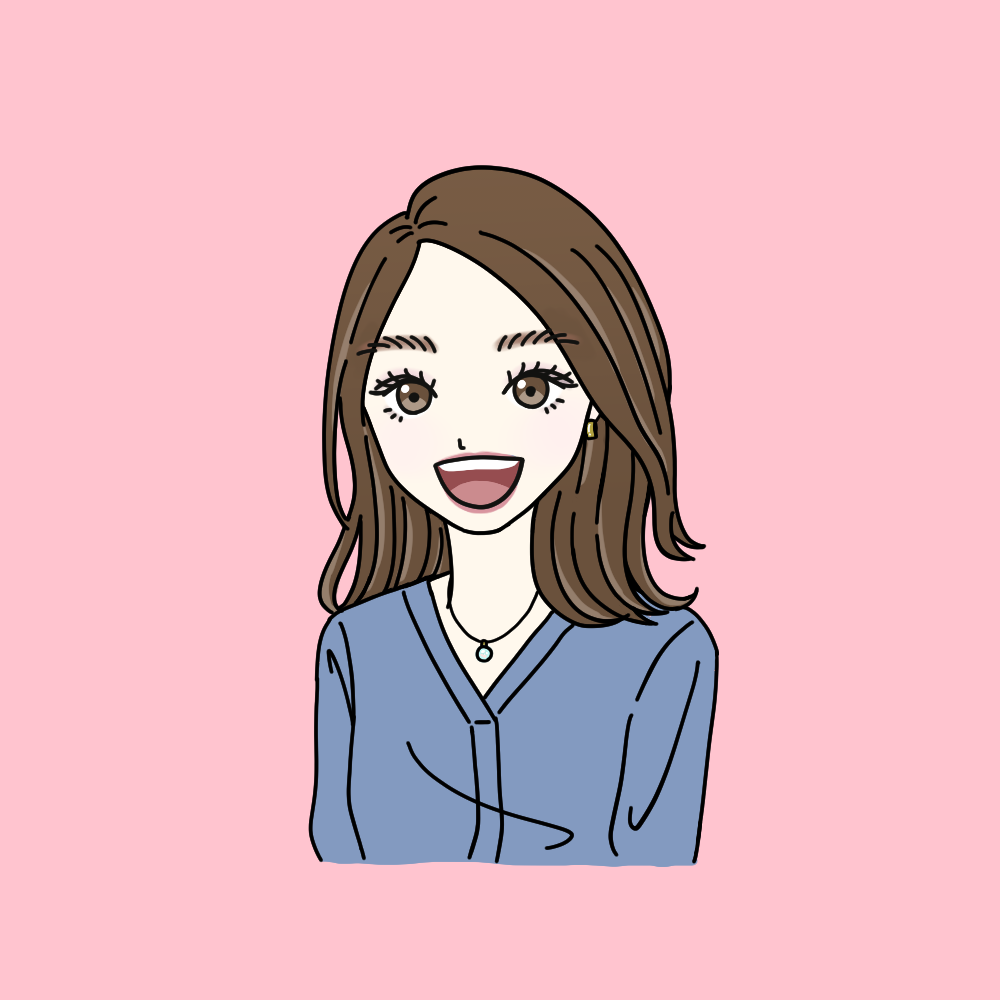
登校後に担任の先生の貴重品箱に預けるという流れを作れば問題ないと思いますが、なかなか進展しません。
交通事故に合わないために、不審者から身を守るために、何度も練習し教えていきましょう。
話だけでは理解しにくいため、一緒に歩いている時、出かけている時、普段日頃から言い続けることが大事になります。
スマホはNGだけどGPSは許可している学校は多々あるそうで、わが家もGPSをもたせます。
最後に・・・
小学校に入学準備としてさまざまなことをあげてきましたが、こどもにとって1番大事なことは、「成長を喜び、学校生活を楽しみ、ワクワクする気持ちをもつこと」です。
そのためには「出来た!」を増やしてあげどんどん褒めることが大事です。
親が気を張りすぎて、「来年から小学校なんだから〇〇しなさい!」と命令が多くなってしまうと、こどもは「小学校は嫌なところ」と認識してしまい悪循環に陥ってしまいます。
親自身も周りと比べて焦ることがありますが、是非こども自身の成長を喜び、長期的に見守っていきましょう。