こどもに、「勉強しなさい!!」と何度も言いたくない。
しかし、現実は早ければ幼児期から、遅くとも小学校では必ず勉強と向き合わなければならなくなります。
少なくとも学内で上位を目指す、又は進学校への進学を考えているなら、学校・学童任せにはしておけない心境があります。
こどもの勉強 に対して悩んだことがない人はほとんどいなく、大抵の人が「どうやらせればいいのか。」「どうすれば効率よくできるのか。」と悩み試行錯誤することと思います。
小学校入学前後を節目に、こどもの勉強との向き合い方をまとめました。
こどもの勉強 ①家庭学習の習慣を身につける
できる子の共通点は、「家で勉強に向かう習慣がある」「勉強ができる環境がある」ことです。
始めから「勉強は塾で。」と塾に任せるのではなく、家で習慣付けをしましょう。小学校入学は一つの節目になるため、新たな習慣を取り入れやすい時期でもあります。
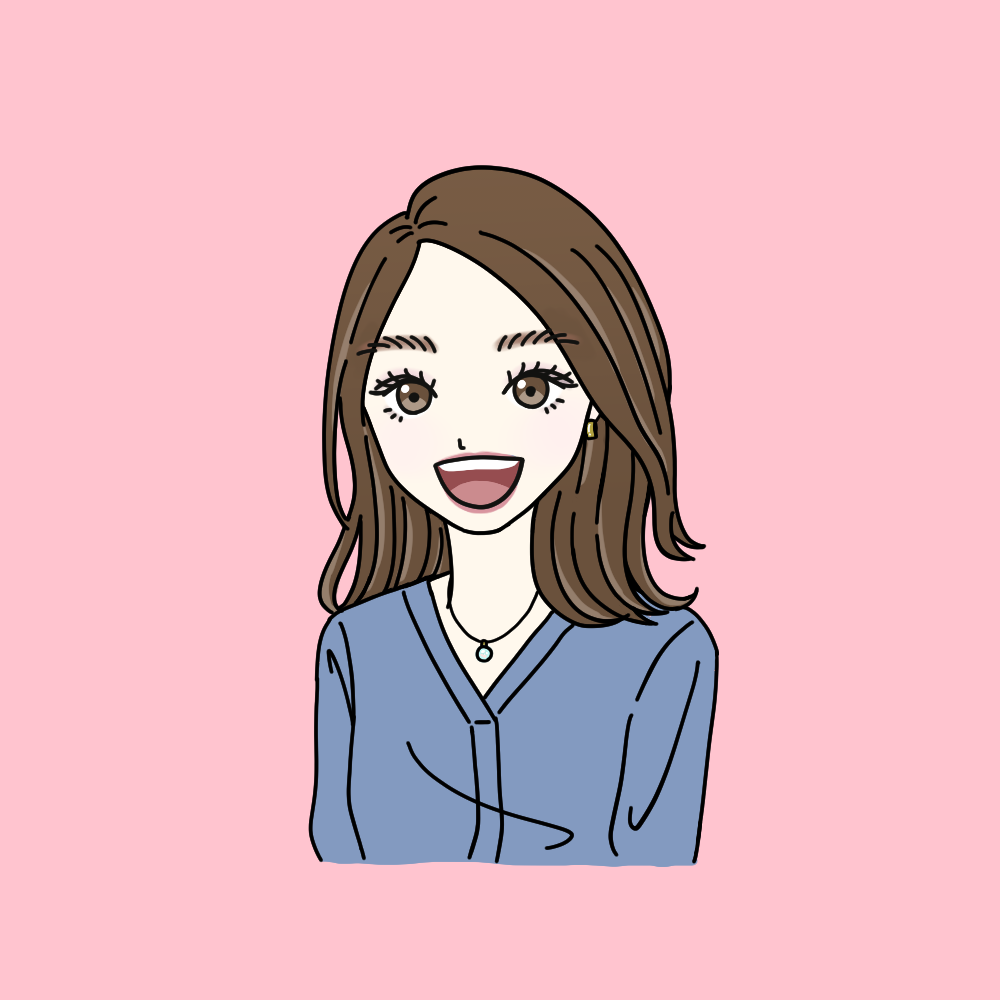
塾でも学校でも必ず宿題はでます。
宿題・復習への取り組み方が、1番差が出るため家庭学習はとても重要!
まずは、1日15分!家庭学習を始める!
お勉強の難易度よりも15分間、座って机に向かうことが大事になります。
達成感と楽しさが継続のカギになるため、運筆・知育要素のある学習から始めることをおすすめします。
【七田式プリント】1日15分!ワーママでも取り組める幼児教育
また、家庭で勉強に向かう時は、テレビや音楽を消して集中できる環境を整えます。
勉強机がある場合、机上にはなるべく物を置かず気が散らない工夫をしましょう。
進度を気にして親本位すぎる目標を立てると、子どもにとって学習が苦痛でしかなくなってしまいます。
習慣がつくと必ず結果がでます。一時の進度や結果に惑わされることなく着実に学習習慣を身に付けることを優先させましょう。
そのためにも、取り組む姿勢や継続する姿勢を褒めることが大事になります。
こどもの勉強 ② 学習のサポートができる時間を確保する
親の時間確保をまず最初に考えます。子どもにやらせるのではなく、自分が一緒にやるつもりで時間を確保することが大事です。
そして、幼児期から小学校低学年までは親のサポートが必要になるため、子どもの学習時間は家事や仕事を詰め込み過ぎずに、すぐサポートできるようにしましょう。
どうしても時間通りにいかないことが続くと、親がイライラしてしまい、怒る・急かすことが増えます。
いつ・どのように取り組むか1日のスケジュールに盛り込みましょう。
「いつ」の設定は時間より行動で決めます。幼稚園・小学校低学年にとって時間で行動するのは少々難しく、時間通りにいかない事も多々あります。
親からイライラした表情が見えると子どものモチベーションは低くなり、最終的には「勉強=怒られる嫌なこと」と認識してしまいます。
多少の時間が前後することは許容範囲とし、それよりも継続することや、どのような姿勢で学習に向かうべきか、を大事にしましょう。
オススメは、起床・朝食・帰宅・お昼寝・夕食・お風呂などの前後に行い、1日のルーティンとセットにすることです。
必ず行う行動と抱き合わせることで、やり忘れを防ぎ習慣化しやすくなります。
その中でも個人的なオススメは朝学習です。朝目覚めてからの3時間は脳のゴールデンタイムと呼ばれ最も脳が効率よく働く時間と言われています。
また、この時間帯は電話や来客もなく家庭のことに集中できるため親も時間を確保しやすくなります。
長女は2才から家庭学習を始め、年長では自ら取り組む姿が見られるようになりました。
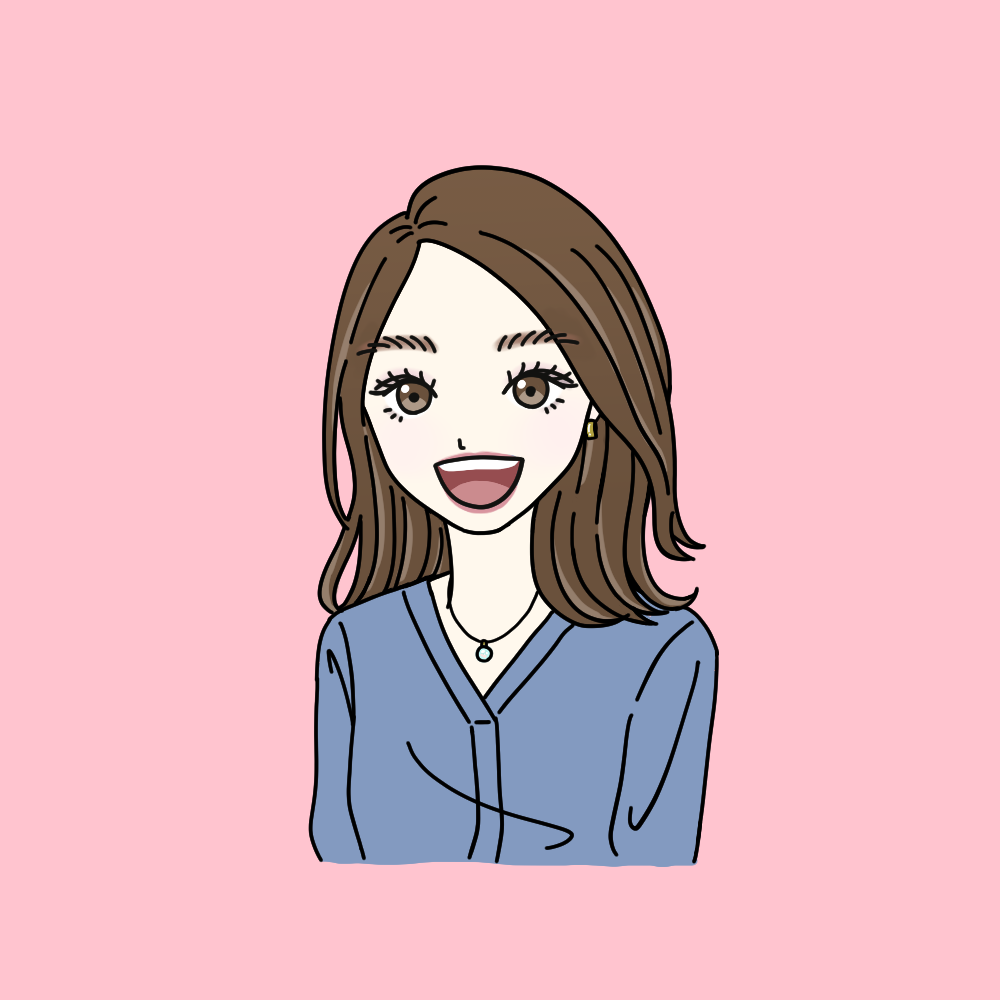
最初は隣に付きっきりでしたが、年中になると1人で取り組むことが増え、家事をしながら朝学習を見ることができるようになりました。
なにより、習慣化にはアップダウンは付きもの!
進度や完成度を重視しすぎると、習慣化する前に辛くなってしまいます。親子の”ちょうどいい加減”でまずは続けることを意識して取り組みましょう。
こどもの勉強 ③ こどもの特性と好き嫌いや得意不得意を把握する
続けていくと必ず、難しい、飽きる、疲れた、なんだかやる気がでない…etc と、つまづきます。
この「嫌だ」という感情が出てきたときに頭ごなしに「いいからやりなさい!」と強制してしまうのはちょっと危険です。
なぜなら「嫌だ」はSOSのサインでもあります。
長女の朝学習で1番最初に「嫌だ」が出たのは公文の随筆運動のプリントでした。
特別難しい内容ではなく、これまで楽しそうに取り組んでいたため、私は「ただ気分がのらないだけだろう。」と思っていました。
しかし後に公文の先生から、「幼児は腕の筋肉が未発達なので、書くだけでも疲れてしまいます。長女ちゃんの限界がきているので、一度枚数を少なくしましょう。」と言われました。
先生が長女のSOSに気づいてくれたためその後、枚数の壁を乗りこえることができましたが、あのまま無理矢理やらせていたら、公文嫌いになっていたかもしれません。
「嫌だ」には理由があること、「嫌だ」の見分け方を知るきっかけとなりました。
家庭学習をすることで、子どもの特性も見えてきます。
時間はかかるが慎重に解くタイプ、容量良く行うがケアレスミスをするタイプ…etc
数字の好き嫌い、読むことの得意不得意、苦手分野に直面したら泣く、怒る、投げ出す…etc
学習を進めるといろんな長所と短所が見えてくるため、学校での様子も想像がつき、何をどうすればいいか見えてきます。
最終的に勉強の出来不出来も物事の考え方、精神面の影響が多く、塾に行っても成績に反映されない原因も子どもの気持ちが置いてきぼりになっていることが考えられます。
長所をのばし、短所は長い目で見守りながら取りくみましょう。
最後に
家庭学習は、受験や学校のためにするものではないと思います。
スケールは大きくなってしまいますが、人生は学びの連続ですし、仕事も学びの集合体です。学び経験しより良い人生を創造することが人生の醍醐味だと考えます。
そのため、思考力を育て、問題解決能力を高め、精神力を鍛えることを学習を通して行っているだけなのです。
進学のための勉強だけではない学ぶ習慣を身につけることは、学生だけに必要なことではなく、むしろ社会人になってからのほうが学ぶ習慣がある人ない人では開きがでてくるものです。
成績をあげるためだけの家庭学習にならないよう、学ぶ習慣を意識して行ってみてください。


